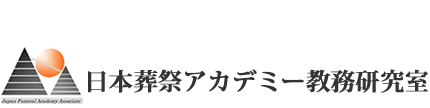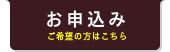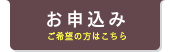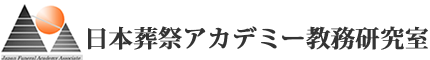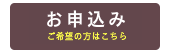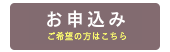桜に見る死生観
日本の「国花」は「桜」。花見といえばこれは桜で、梅は梅見、観梅など別の言葉遣いをする。
桜の語源については諸説あり、「さ」は榊(さかき)の「さ」で、神様を表し、また「幸」の「さ」という説もある。「くら」は、学説的に異論なく「神座」(かみくら)の「くら」。稲作民俗の影響が強い日本人にとって、桜は田の神がおわすところ、依り代として、その開花は、神の意思の表れとして、受け止めていたようである。
あわせて、桜の花の趣はやはり潔い「散り際」にある。この感性が日本人の死生観を美学として映し出してきたといってもよい。
死はともに大きな「節目」であり「けじめ」でもある。葬式を営むことは通過儀礼。通り過ぎていくことを前提とした「通過点」に対する儀礼である。
決して「終着点」ではなく、むしろ「旅立ち」と考えている。そのために来るべき「次」の場面や次元に備えるための「演習」を、葬送儀礼のなかで意図しているものも多い。
ともすれば、生前の思い出や追慕の念、あるいはその生き様を偲ばせることだけがお葬式の目的のように思うが、死を起点に、そこから「先」の対応を指し示すというような儀礼意識は皆無になってしまった。仏教葬儀の「往生」や「成仏」も死語となり、そのため葬儀後の「供養」と季節儀礼や人生儀礼とのかかわりも不明となってしまい、先祖意識も遠のいてしまった。家系とか血脈という、自分の人生だけでは図ることの出来ない永続性に、気が付かないまま、死は取り図られていく。「個人的」な思慕だけが、遺された者の感情であり、一方で「その人らしさ」を表出させることが「サービス」だとおもっている葬儀社も多い。
桜の花の散り際、そこを眺める感性が葬祭業には必要である。